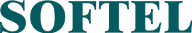現代の光通信システムでは、より高い容量とより長い伝送距離の追求において、根本的な物理的制限であるノイズが常にパフォーマンスの向上を制限してきました。
典型的なEDFAエルビウム添加光ファイバー増幅システムでは、各光伝送スパンで約 0.1dB の累積自然放出ノイズ (ASE) が生成されますが、これは増幅プロセス中の光と電子の相互作用の量子ランダム性に起因します。
このタイプのノイズは、時間領域においてピコ秒レベルのタイミングジッタとして現れます。ジッタモデルの予測によると、分散係数が30ps/(nm · km)の条件下では、1000km伝送時にジッタが12ps増加します。周波数領域では、光信号対雑音比(OSNR)の低下を招き、40Gbps NRZシステムにおいて3.2dB(@ BER=1e-9)の感度損失をもたらします。
より深刻な課題は、光ファイバの非線形効果と分散の動的結合です。従来のシングルモード光ファイバ(G.652)の1550nm波長域における分散係数は17ps/(nm · km)であり、これに自己位相変調(SPM)による非線形位相シフトが加わります。入力パワーが6dBmを超えると、SPM効果によってパルス波形が著しく歪みます。

上図に示す960Gbps PDM-16QAMシステムでは、200km伝送後のアイ開口度は初期値の82%であり、Q値は14dB(BER≈3e-5に相当)に維持されています。距離が400kmに延長されると、相互位相変調(XPM)と四光波混合(FWM)の複合効果により、アイ開口度が63%に急激に低下し、システムエラー率がハード決定FECエラー訂正限界の10^-12を超えます。
注目すべきは、直接変調レーザー(DML)の周波数チャープ効果が悪化することです。一般的なDFBレーザーのアルファパラメータ(線幅増大係数)値は3〜6の範囲にあり、その瞬間周波数変化は1mAの変調電流で±2.5GHz(チャープパラメータC = 2.5GHz / mAに相当)に達する可能性があり、80kmのG.652ファイバーを伝送した後、パルス広がり率は38%(累積分散D・L = 1360ps / nm)になります。
波長分割多重(WDM)システムにおけるチャネルクロストークは、より深刻な障害となります。50GHzのチャネル間隔を例にとると、四光波混合(FWM)によって引き起こされる干渉電力は、通常の光ファイバーでは実効長Leffが約22kmになります。
波長分割多重(WDM)システムにおけるチャネルクロストークは、より深刻な障害となります。50GHzのチャネル間隔を例にとると、四光波混合(FWM)によって生成される干渉電力の実効長はLeff=22km(光ファイバ減衰係数α=0.22dB/kmに相当)です。
入力電力が+15dBmに増加すると、隣接チャネル間のクロストークレベルが7dB(-30dBのベースラインに対して)増加するため、システムは前方誤り訂正(FEC)の冗長度を7%から20%に増加させる必要があります。誘導ラマン散乱(SRS)による電力伝達効果により、長波長チャネルでは1キロメートルあたり約0.02dBの損失が発生し、C+Lバンド(1530~1625nm)システムでは最大3.5dBの電力低下が発生します。ダイナミックゲインイコライザ(DGE)によるリアルタイムのスロープ補償が必要です。
これらの物理的影響を組み合わせたシステム性能の限界は、帯域幅距離積 (B · L) によって定量化できます。G.655 ファイバー (分散補償ファイバー) の一般的な NRZ 変調システムの B · L は約 18000 (Gb/s) · km ですが、PDM-QPSK 変調とコヒーレント検出技術を使用すると、この指標は 280000 (Gb/s) · km (@ SD-FEC ゲイン 9.5dB) まで向上します。
最先端の7コア×3モード空間分割多重光ファイバ(SDM)は、弱結合コア間クロストーク制御(<-40dB/km)により、実験室環境で伝送容量15.6Pb/s・km(単芯容量1.53Pb/s×伝送距離10.2km)を実現しました。
シャノン限界に近づくために、現代のシステムは確率シェーピング(PS-256QAM、0.8dBのシェーピングゲインを達成)、ニューラルネットワークイコライゼーション(NL補償効率が37%向上)、および分散ラマン増幅(DRA、ゲインスロープ精度±0.5dB)技術を共同で採用して、シングルキャリア400G PDM-64QAM伝送のQ係数を2dB(12dBから14dB)増加させ、OSNR許容値を17.5dB/0.1nm(@ BER=2e-2)に緩和する必要があります。
投稿日時: 2025年6月12日