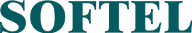光ファイバー通信の世界では、光の波長の選択は無線周波数の調整やチャンネル選択に似ています。正しい「チャンネル」を選択することによってのみ、信号を明瞭かつ安定的に伝送することができます。なぜ光モジュールの中には伝送距離がわずか500メートルしかないものもあれば、数百キロメートルを超えるものもあるのでしょうか?その謎は、光線の「色」、より正確には光の波長にあります。
現代の光通信ネットワークでは、異なる波長の光モジュールがそれぞれ全く異なる役割を果たしています。850nm、1310nm、1550nmの3つのコア波長は光通信の基本的な枠組みを形成し、伝送距離、損失特性、適用シナリオの観点から明確な役割分担が図られています。
1.なぜ複数の波長が必要なのでしょうか?
光モジュールにおける波長多様性の根本的な原因は、光ファイバー伝送における2つの大きな課題、すなわち損失と分散にあります。光信号が光ファイバーで伝送されると、媒体による吸収、散乱、漏洩によってエネルギーの減衰(損失)が発生します。同時に、異なる波長成分の伝播速度の不均一性は、信号パルスの広がり(分散)を引き起こします。このため、多波長ソリューションが生まれました。
•850nm帯:主にマルチモード光ファイバーで動作し、伝送距離は通常数百メートル(約 550 メートルなど)に及び、短距離伝送(データセンター内など)の主力となります。
•1310nm帯:標準的なシングルモード光ファイバーでは低分散特性を示し、伝送距離は最大数十キロメートル(約 60 キロメートルなど)に達し、中距離伝送のバックボーンとなります。
•1550nm帯:減衰率が最も低く(約0.19dB/km)、理論上の伝送距離は150kmを超えるため、長距離、さらには超長距離伝送の王者となります。
波長分割多重(WDM)技術の台頭により、光ファイバーの伝送容量は飛躍的に増加しました。例えば、単芯双方向(BIDI)光モジュールは、送信側と受信側で異なる波長(例えば1310nm/1550nmの組み合わせ)を使用することで、1本の光ファイバーで双方向通信を実現し、光ファイバー資源を大幅に節約します。さらに高度な高密度波長分割多重(DWDM)技術は、特定の帯域(例えばOバンド1260~1360nm)において非常に狭い波長間隔(例えば100GHz)を実現し、1本の光ファイバーで数十、あるいは数百もの波長チャネルをサポートできるため、総伝送容量はTbpsレベルにまで向上し、光ファイバーの潜在能力を最大限に引き出します。
2.光モジュールの波長を科学的に選択するにはどうすればよいでしょうか?
波長を選択する際には、以下の重要な要素を総合的に考慮する必要があります。
伝送距離:
短距離(≤ 2km):850nm(マルチモード ファイバー)が望ましい。
中距離(10〜40km):1310nm(シングルモードファイバー)に適しています。
長距離(60km以上):1550nm(シングルモードファイバー)を選択するか、光増幅器と組み合わせて使用する必要があります。
容量要件:
従来事業:固定波長モジュールで十分。
大容量・高密度伝送:DWDM/CWDM技術が必要です。例えば、Oバンドで動作する100G DWDMシステムは、数十の高密度波長チャネルをサポートできます。
コストの考慮:
固定波長モジュール:初期単価は比較的安いですが、複数波長モデルのスペアパーツを在庫しておく必要があります。
調整可能な波長モジュール: 初期投資は比較的高額ですが、ソフトウェアによる調整により、複数の波長をカバーし、スペアパーツの管理を簡素化し、長期的には運用と保守の複雑さとコストを削減できます。
適用シナリオ:
データ センター相互接続 (DCI): 高密度、低電力の DWDM ソリューションが主流です。
5G フロントホール: コスト、レイテンシ、信頼性に対する要件が高いため、産業グレードで設計されたシングル ファイバー双方向 (BIDI) モジュールが一般的な選択肢です。
エンタープライズ パーク ネットワーク: 距離と帯域幅の要件に応じて、低電力、中距離から短距離の CWDM または固定波長モジュールを選択できます。
3.結論:技術の進化と将来の考察
光モジュール技術は急速に進化を続けています。波長選択スイッチ(WSS)や液晶オンシリコン(LCoS)といった新しいデバイスは、より柔軟な光ネットワークアーキテクチャの開発を牽引しています。Oバンドなどの特定の帯域をターゲットとしたイノベーションは、十分な光信号対雑音比(OSNR)マージンを維持しながらモジュールの消費電力を大幅に削減するなど、パフォーマンスの最適化を継続的に進めています。
今後のネットワーク構築において、エンジニアは波長選択時に伝送距離を正確に計算するだけでなく、消費電力、温度適応性、展開密度、ライフサイクル全体の運用保守コストを総合的に評価する必要があります。-40℃の極寒環境など、極限環境下でも数十キロメートル安定して動作できる高信頼性光モジュールは、複雑な展開環境(遠隔基地局など)を支える重要な基盤となりつつあります。
投稿日時: 2025年9月18日